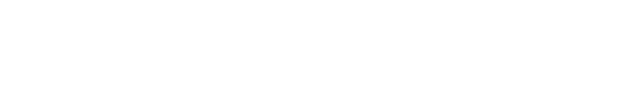歯周病の治療方法
歯周病(歯槽膿漏)とは
歯の周囲に汚れがたまることで、歯茎に炎症が生じます。この炎症が続くと歯を支えている骨まで炎症により溶けていってしまし、歯が揺れてきます。そして、いずれは骨が歯を支えられなくなり抜けてしまいます。この骨が溶けていく症状を歯周病(歯槽膿漏)と言います。
比較的早い段階で現れる症状としては「歯茎の腫れ」「歯みがき時の出血」「口臭」等があります。
ただ、歯周病は基本的に痛みの無い病気なので、自身で気づくことができず、「歯が揺れている」など気がついたときには重症化しており、抜歯せざるを得ないことが多い病気でもあります。
歯を失う最大の原因は歯周病
歯周病は歯が抜けてしまう一番の原因と言われています。
気がついたときには手遅れ、、、なんてこともよくありますので、無症状の内から予防していくことが非常に重要です。
歯周病と全身疾患
歯周病は歯の問題だけでは無く、歯周病菌が血液中に入り、全身を巡ることで歯科のような漸進的な病気の原因となることが知られています。
特に糖尿病は歯周病と関係が深く、歯周病にかかっていると糖尿病になる確率が2.6倍も高くなると言った調査結果もあります。また、糖尿病の方が歯周病治療をされると、糖尿病の具合が改善することも報告されています。
狭心症・心筋梗塞
歯周病菌の刺激により動脈硬化を誘導する物質が出て血管内にプラーク(粥状の脂肪性沈着物)が出来血液の通り道は細くなります。
プラークが剥がれて血の塊が出来ると、その場で血管が詰まったり、血管の細いところで詰まります。これにより、心筋に血液供給がなくなり死に至ることもある病気です。
脳梗塞
脳の血管にプラーク(歯周病菌)が詰まったり、頸動脈や心臓から血の塊やプラークが飛んで来て脳血管が詰まる病気です。歯周病の人はそうでない人の2.8倍脳梗塞になり易いと言われています。
血圧、コレステロール、中性脂肪が高めの方は、動脈疾患予防のためにも歯周病の予防や治療は、より重要となります。
低体重児出産
妊娠している女性が歯周病に罹患している場合、低体重児および早産の危険度が高くなることが指摘されています。
これは口の中の歯周病細菌が血中に入り、胎盤を通して胎児に直接感染するのではないかといわれています。その危険率は実に7倍にものぼるといわれ、タバコやアルコール、高齢出産などよりもはるかに高い数字なのです。
※日本臨床歯周病学会参照
糖尿病
歯周病菌は腫れた歯肉から容易に血管内に侵入し全身に回ります。血管に入った細菌は体の力で死滅しますが、歯周病菌の死骸の持つ内毒素は残り血糖値に悪影響を及ぼします。血液中の内毒素は、脂肪組織や肝臓からのTNF-αの産生を強力に推し進めます。
TNF-αは、血液中の糖分の取り込みを抑える働きもあるため、血糖値を下げるホルモン(インスリン)の働きを邪魔してしまうのです。
※日本臨床歯周病学会参照
誤嚥性肺炎
誤嚥性肺炎とは、食べ物や異物を誤って気管や肺に飲み込んでしまうことで発症する肺炎です。肺や気管は、咳をすることで異物が入らないように守ることができます。しかし、高齢になるとこれらの機能が衰えるため、食べ物などと一緒にお口の中の細菌を誤嚥してしまい、細菌が気管から肺の中へ入ることがあります。誤嚥性肺炎の原因となる細菌の多くは、歯周病菌であると言われており、誤嚥性肺炎の予防には歯周病のコントロールが重要になります。
骨粗鬆症
閉経後骨粗鬆症の患者さんにおいて、歯周病が進行しやすい原因として最も重要と考えられているのが、エストロゲンの欠乏です。
エストロゲンの分泌が少なくなると、全身の骨がもろくなるとともに、歯を支える歯槽骨ももろくなります。また、歯周ポケット内では、炎症を引き起こす物質が作られ、歯周炎の進行が加速されると考えられています。
関節炎・腎炎
関節炎や糸球体腎炎が発症する原因のひとつとして、ウィルスや細菌の感染があります。
関節炎や糸球体腎炎の原因となる黄色ブドウ球菌や連鎖球菌の多くは、歯周病原性細菌など口腔内に多く存在します。
これらのお口の中の細菌が血液中に入り込んだり、歯周炎によって作り出された炎症物質が血液に入り込むことで、関節炎や糸球体腎炎が発症することがあります。
メタボリックシンドローム
詳しいメカニズムは解明されていませんが、歯周病の病巣から放出されるLPS(歯周病菌由来の毒素)やTNFαは脂肪組織や肝臓のインスリン抵抗性を増加させ、血糖値を上昇させます。
また、重度歯周病患者では血中CRP値が上昇し、動脈硬化や心筋梗塞発症のリスク亢進と密接に関与すると考えられています。
さらには、この慢性炎症が個体の老化を促進するという論文も出てきました。
このように歯周病とメタボリックシンドロームの関連性が注目されています。
歯周病の進行段階
第1段階 歯肉炎
歯茎だけが腫れており、骨に異常は生じていない状態です。痛みや違和感はほとんどありません。歯みがきをしっかりして、歯科医院でクリーニングや歯石除去などを行えば、健康な歯肉への改善が期待できます。しかし、歯肉炎を放置すると第2段階の「歯周炎」に移行します。
第2段階 軽度歯周炎
歯茎の腫れだけでなく、歯を支えている歯槽骨が溶け始めた状態です。「歯みがきをすると出血する」といったことが症状が出始めますが、ほとんどの場合で自覚症状はありません。歯科医院でクリーニングや歯石除去などを行い改善を図ります。
第3段階 中等度歯周病
歯槽骨が歯の根の半ばくらいまで溶けている状態です。「歯が揺れている」「口臭がする」と言った自覚症状が出始めます。通常のクリーニングや歯石除去では対応できないケースが多く、歯周外科治療が必要な場合があります。
第4段階 重度歯周病
歯茎は下がり、歯が大きくぐらついて状態です。残っている歯を少しでも長く残せるように、歯槽骨を再生させる治療方法などを提案できる場合もありますが、残念ながら抜歯になることも少なくありません。この段階に至らないように予防することが非常に大切です。
歯周病は治るのか?
歯周病は歯を支えている歯槽骨が溶けてしまう病気です。この溶けてしまった骨を元通りにすることは非常に困難であり、基本的にはできないとされています。当院でも一部省令に対しては骨を再生させる「再生療法」を行うことで骨の再生を図りますが、完全に元に戻すことは非常に難しいので「歯周病は改善できる」という考えを指標にしています。
例えば、こけたりしたときの擦り傷は時間をおけば元通りに治るでしょう。このように元に戻ることは歯周病治療に対しては期待できません。
それに対し、指先を切断してしまった場合、断面の傷は治りますが、指がそこから生えてきて元に戻ることはありません。歯周病治療もすでに無くなってしまった骨が再生することは現時点では非常に困難です。
歯周病治療の流れ
STEP4
<歯周病治療開始>
歯周病の進行の段階にあわせ、ステップを踏んで治療を進めていきます。
①スケーリング(浅い歯石取り)
②SRP(深い歯石取り)
③歯周外科治療・再生療法
STEP5
<メインテナンス>
歯周病は非常に再発しやすい病気です。年齢と共に免疫が低下することでも発症しやすくなります。歯周病の予防・再発防止には継続した管理とメインテナンスが不可欠です。
歯周病治療
①スケーリング
スケーリングと呼ばれる器具で、歯の表面や、歯茎の下に隠れている歯垢や歯石を除去することです。
当院では患者様の状態に応じ「手用スケーラー」「エアスケーラーTi-Max S970」「超音波(Varios970)「超音波(ピエゾSⅡ)」と4種の器具を使い分け、『痛みがないように治療して欲しい』『治療回数を少なく一気に治して欲しい』といったご要望にお応えできるようにしています。
②ルートプレーニング:SRP
歯周病が中等度以上に進むと、歯周ポケットが深くなるため、スケーリングだけでは奥深くに隠れている歯石を取ることができません。この場合にキュレットという器具を使用し、奥深くの歯石や感染した歯質をキレイに取り除くルートプレーニングを行います。この処置により、歯の根の表面を滑らかにし歯茎が歯にしっかりくっつくようにしていきます。
③歯周外科治療・再生療法
中等度~重度の歯周病には手術が必要になることがあります。
歯周外科治療
歯茎の底深くに歯石がついていると、歯茎が邪魔で歯石がとれない、歯の表面を磨き上げられないため歯周病が治りにくいことがあります。この場合は、歯肉を切って剥離し、歯肉の下に隠れていた歯石を見える状態にして、スケーリングやルートプレーニングでは除去しきれない部分までキレイにしていきます。
再生療法
適用できる症例は限られますが、歯周外科治療の際に、「リグロス」と呼ばれる薬や、骨の足場となる「骨補填剤」を用いることで、歯周病で溶けてしまった骨を再生させられる可能性を持った治療方法があります。
歯周病予防、再発防止
ご自身での歯みがき、定期的なメインテナンスが歯周病予防には非常に大切です。どれだけキレイに磨いていても、お口の中の汚れを全て取り切ることはなかなかできることではありません。歯周病が進行してしまってからでは、治療の回数も内容も大変になってしまします。悪くならないように歯科医院でプロフェッショナルケアを受けましょう。